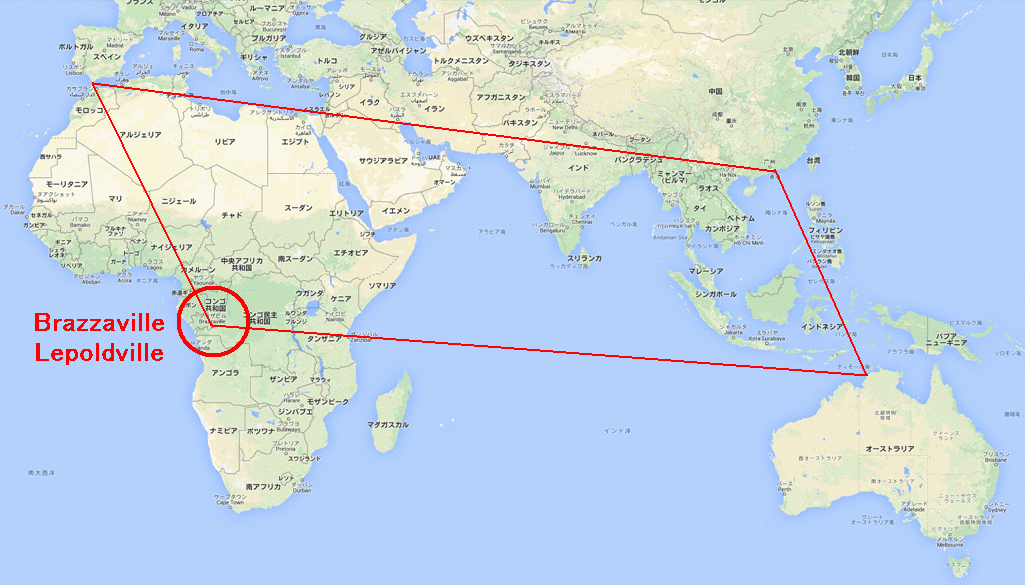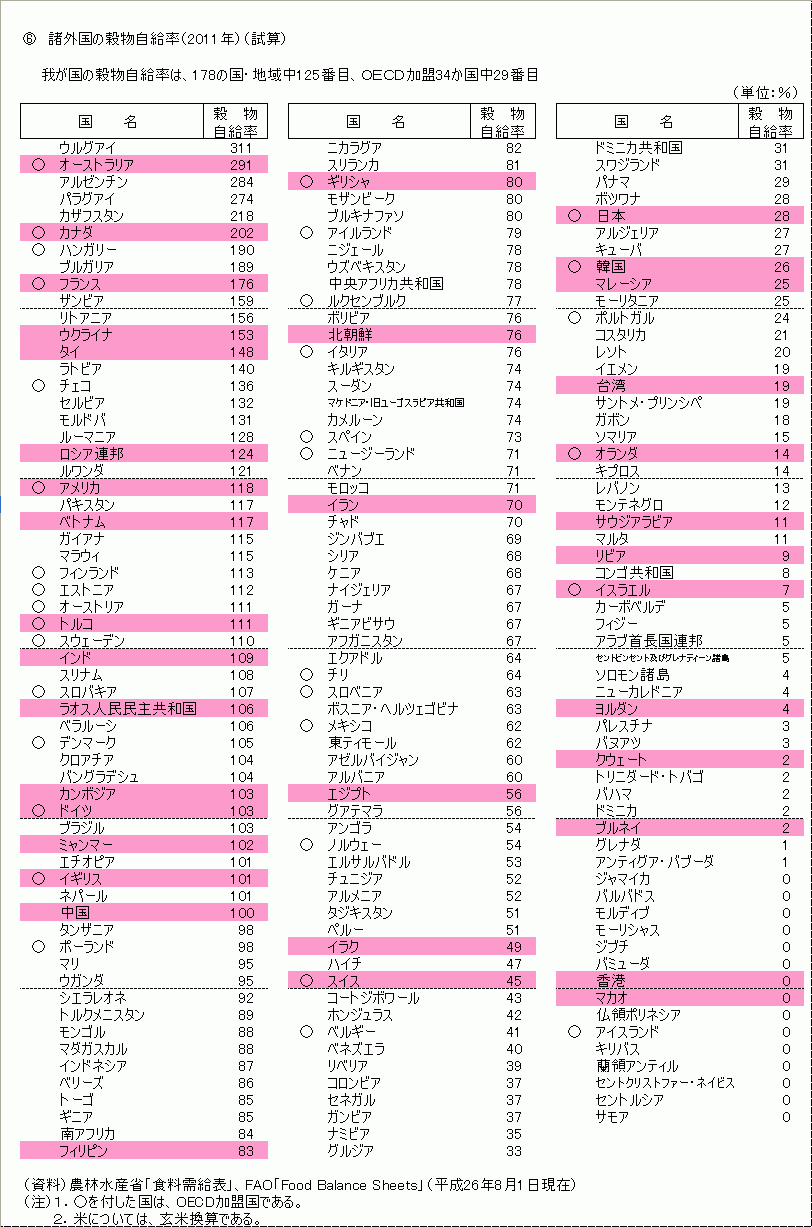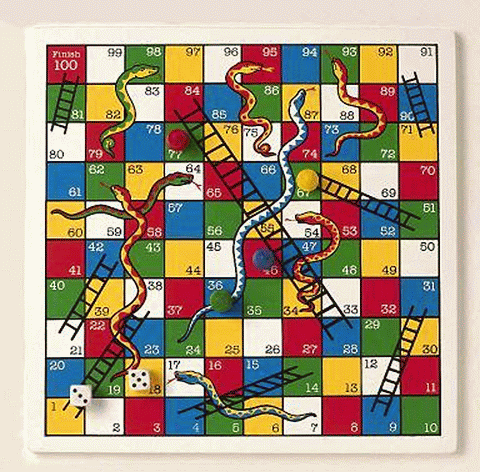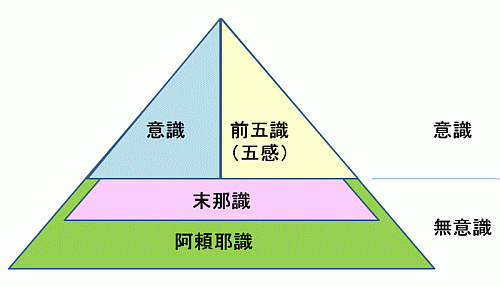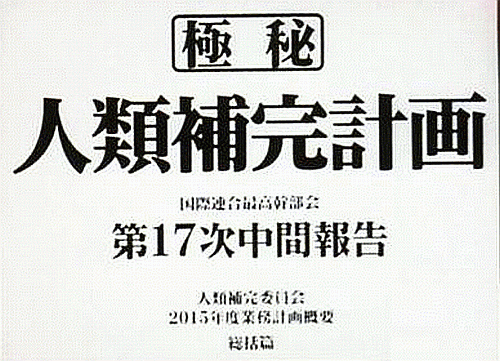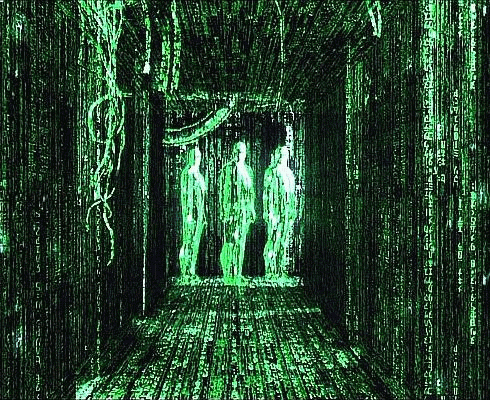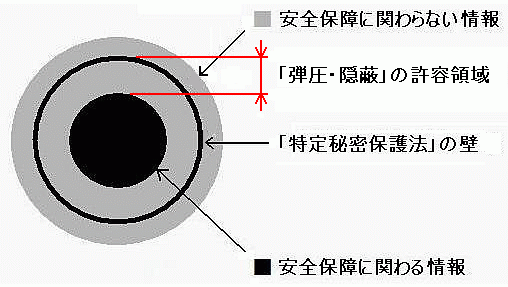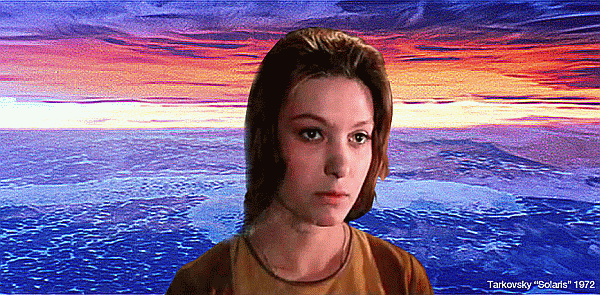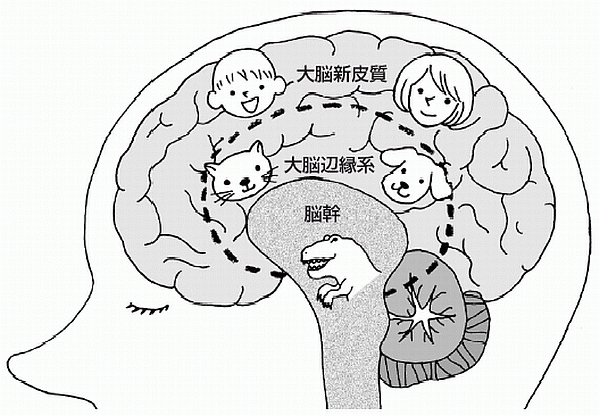第三部
第二章
(01)
彼はなにか折り畳み式のベッドのようなものに横たわっていた。ただしそれは床からだいぶ高く、その上に動けないように固定されていた。顔はまぶしい光で照らされている。
脇にオブライエンが立ち、じっと彼を見下ろしていた。その反対側には白い上着を着た男が注射器を手に立っている。
(02) 目を開いた後も彼には周りの様子がゆっくりとしか見えてこなかった。
自分がどこか全く異なる世界、深い水底の世界からこの部屋に浮かび上がったような印象を彼は受けた。どれだけの間そこに横たわっていたのかはわからなかった。逮捕された瞬間から暗闇も陽の光も見ていないのだ。
とにかく記憶は途切れていた。眠りに落ちた時にも残っているようなわずかな意識さえ無い空白の時間があり、その後で再び意識を取り戻すということが何回か続いた。しかしその時間が数日だったのか数週間だったのか、あるいはほんの数秒だったのかそれを知るすべは無かった。
(03)
肘への最初の一撃によって悪夢は始まったのだ。後になって彼は、その時に起きたことは囚人であればほぼ全員が経験するものであり、一連の取り調べのたんなる予告に過ぎないことを知った。当然のように皆が自白しなければならない犯罪は多かった・・・スパイや破壊活動といったものだ。
自白は形式的なものにすぎなかったが拷問は本物だった。何回殴られたか、どれだけの間殴り続けられたか、彼には記憶がない。
いつも黒い制服を着た5、6人の男がいた。ある時は拳で、ある時は警棒で、ある時は鉄の棒で、ある時はブーツで彼は打たれた。時には身を捩りながら、動物のように恥も外聞もなく床に転がることもあった。それは蹴りを避けようという終わりも希望も無い努力だったが、たんに肋骨や腹、肘、すね、股間、睾丸、腰骨にさらなる蹴りを招くだけだった。看守が自分を殴り続けることではなく、
自分で意識を失えないことが冷酷で邪悪で無慈悲なことだと考えだすほどそれが続く時もあった。神経が参ってしまって殴られる前から許しを乞う叫びを上げることもあったし、拳を見ただけで殴られたようになって自分の犯した罪についてある事ない事、次々に自白することもあった。そうかと思うと何も自白しないと決意することもあったし、
全ての言葉が痛みの喘ぎ声と共に無理やり引き出されることもあった。また弱々しく譲歩を試みる時もあったし、「自白しよう。だがまだだ。
痛みに耐えられなくなるまでは我慢だ。あと三回蹴られたら、あと二回蹴られたら、そうしたら奴らの好きなようにしゃべってやる」そう自分に言い聞かせることもあった。時には立っていられなくなるまで殴られ、
じゃがいも袋のように監房の石造りの床に倒れこむこともあった。そうなると回復するまで数時間、放っておかれ、それからまた連れて行かれて殴られるのだった。回復のために長い期間が取られることもあった。ほとんどの場合は眠っていたり意識不明の状態だったので、その時のことはおぼろげにしか憶えていない。憶えているものは、まるで壁に取り付けられた棚のような板張りのベッドのある監房、ブリキの洗面器、それに温かいスープとパンの食事、
たまに出るコーヒーだった。また理髪師があごひげを剃り、髪を刈りに来たことや、
白い上着を着た事務的で無表情な男たちが彼の脈を取り、反射反応を調べ、まぶたをめくり、骨折箇所を調べるために乱暴に体に指を走らせ、眠らせるために腕に注射針を打ち込んだことを確かに憶えていた。
(04) やがて殴られることが少なくなり、彼の受け答えが十分でない場合には脅されたり、恐ろしい目にあわせられるようになった。
尋問者は黒い制服を着たごろつきではなく、眼鏡を光らせた動きのすばしっこい小太りの党のインテリになっていた。彼らは代わる代わる交代で一度に・・・彼には確認しようもなかったが・・・10時間も12時間もの間、尋問を続けた。この尋問者たちは常に軽い痛みを彼に与えたが、
彼らの武器は苦痛ではなかった。たしかに彼らは顔をはたいたり、耳を捻りあげたり、髪をつかんだり引きずったり、片足で立たせ続けたり、トイレに行くことを禁じたり、目から涙が流れるまでぎらぎらと輝く明かりで彼の顔を照らしたりした。しかしその目的は
彼に屈辱を与え、反論したり論理的に考えたりする力を奪い取ることだった。彼らの武器は何時間も続く容赦のない尋問だったのだ。揚げ足をとり、罠にはめ、彼の言ったこと全てをねじ曲げ、恥辱と神経の疲れで彼が泣き出すまで全てを嘘や矛盾だと決めつけた。
時には一度の取り調べで六回も彼が泣き出したことさえあった。ほとんどの時間、彼らは罵りの叫びを上げ続け、彼が口ごもるたびにまた看守のところに送り込むぞと脅した。しかし時には突然態度を変えて彼を同志と呼び、イングソックとビッグ・ブラザーの名前を出して訴えかけることもあった。そして過ちをあがないたいという思いを抱かせる党への忠誠心は今もないのか、と悲しそうに尋ねるのだ。何時間もの尋問の後で彼の神経がぼろぼろになっている時には、そんな訴えでさえも彼にすすり泣きの涙を催させた。
最後の方にはその執拗な声は、看守のブーツや拳よりも完璧に彼を打ちのめした。要求されれば何でもしゃべる口に、そして何にでも署名する手に彼は成り下がった。
虐待行為が新たに始まる前に彼らが自白させたいことを見付け出し、すばやく自白する。それだけが彼の関心ごとだった。彼は地位の高い党員の暗殺を、扇動的なビラの配布を、公的資金の横領を、軍事機密を売り渡したことを、あらゆる種類の破壊活動を自白した。
はるか昔、1968年からイースタシア政府に雇われたスパイであったことを自白した。また自分が宗教信者であり、資本主義の信奉者であり、性的倒錯者であることを自白した。
自分の妻を殺したことも自白した。彼も、そして尋問者も、間違いなく妻がまだ生きていることを知っているのにも関わらずだ。何年もの間、ゴールドスタインと個人的な接触があること、地下組織のメンバーであることを彼は自白した。
彼の知り合いのほとんどが、同じ組織に所属することも付け加えた。そうすることでどんなことでも自白しやすくなったし、誰でも巻き込むことが容易になった。さらに言えば
ある意味で自白は全て真実だった。彼が党の敵対者であることは真実だったし、
党の目から見れば思想と行動の間に区別は存在しないのだ。
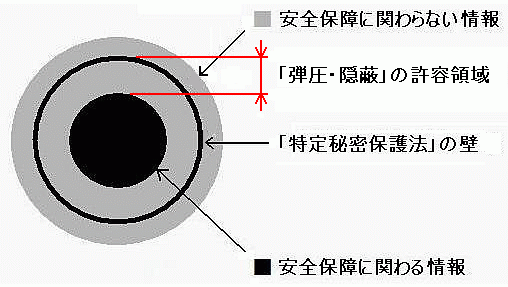
(05) 他にも憶えていることはあったが、それはまるで暗闇の中にちらばる絵のような途切れ途切れの記憶だった。
(06) 彼は暗いのか明るいのかもわからない監房にいた。
彼には一対の目玉だけしか見えないのだ。近くでは何かの装置がゆっくりと規則的な音をたてている。目玉はだんだん大きく、鮮明になっていく。
突然、彼はいすから浮き上がり、その目玉に向かって飛び込み、飲み込まれた。
(07)
まばゆい光の下で彼は計測器に囲まれたいすに縛り付けられていた。白い上着を着た男が計測器を読み取っている。外から重々しいブーツの足音が聞こえ、扉が音をたてて開くと蝋人形のような顔の
執行官が二人の看守を従えて歩いてきた。
(08)
「101号室だ」執行官が言った。
(09) 白い上着の男は顔も上げない。ウィンストンの方も見てはおらず、ただ計測器だけを見つめていた。
(10) 彼は大きな笑い声と自白の叫びをあげながら、
幅が1キロほどもある壮麗で黄金の光が満ちた巨大な廊下を転げ落ちていった。彼は全てを自白していた。拷問で守り通したことまでもだ。自分の生涯を既にそれを知っている聴衆に向けて語っていた。看守たち、尋問者たち、白い上着の男たち、オブライエン、ジュリア、チャーリントン氏、
皆が彼と一緒に高笑いしながら廊下を転げ落ちていった。未来に必ず起きるはずだった恐ろしい出来事は、どうしたわけかいつの間にか通り過ぎ、起こらなかった。全てが順調で、痛みはもう存在しなかった。
彼の人生は隅から隅まで暴かれ、理解され、許されたのだ。
(11) 彼はオブライエンの声を聞いたような気がして板張りのベッドから起き上がろうとした。彼の姿は見えなかったが尋問の様子から、オブライエンが自分の肘のあたりのちょうど視界から外れている場所にいるような気がした。
全ての指揮を下していたのはオブライエンだった。ウィンストンを看守の手に引き渡し、なおかつ彼らに殺させないようにしていたのは彼だったのだ。いつウィンストンが痛みに叫びを上げるべきか、休息をとるべきか、食事を与えられるべきか、眠るべきか、腕に薬物を注射されるべきか、彼が決めていたのだ。質問を尋ね、その答えに誘導していたのは彼だったのだ。
彼は虐待者であり、庇護者であり、尋問官であり、友人だった。そして・・・薬で眠らされていた時だったか、普通に眠っている時だったか、目覚めている時だったかすら彼は憶えていなかったが・・・声が彼の耳につぶやいた。「心配するな、ウィンストン。君は私が守っている。
七年間、君を見守ってきた。今、転換点が来たんだ。
君を助けて、完璧にしてやる」オブライエンの声だったかどうか彼にはわからなかったが、それは七年前に夢の中で
「暗闇でない場所で会うことにしよう」と彼に言ったのと同じ声だった。
(12) どんな風に尋問が終わったのかは憶えていなかった。暗転の時間があり、それからだんだんと彼が今いる監房、あるいは部屋が彼の周りに浮き上がってきた。
彼の体はほぼ水平になっていて身動きすることはできなかった。体が要所要所で固定されていたのだ。後頭部すら何らかの方法で固定されていた。
オブライエンが厳しい顔でとても悲しそうに彼を見下ろしていた。下から見ると彼の顔は疲れきって荒れ、目の下はたるみ、鼻からあごにかけて疲労によるしわができていた。彼はウィンストンが思っていたよりも年老いていた。
おそらく48歳か、50歳といったところだろう。彼の手の下には上部にレバーがついたダイヤルがあり、その周りには数字がふられていた。
(13)
「また会うとしたらそれはここだろう、と私は君に言ったな」オブライエンが言った。
(14)
「ええ」ウィンストンが言った。
(15)
オブライエンの手がわずかに動いただけで、他には
何の警告もなく痛みの波が彼の体に流れ込んだ。それはぞっとするような痛みだった。彼には何が起きたのか分からず、何か致命的な負傷が自分に起きたように感じられた。何かが本当に起きているのか、それともたんなる電気的に生み出された結果なのかが彼にはわからなかった。しかし
体は奇妙な形にねじ曲がり、関節がゆっくりと引き裂かれていくようだった。痛みで額から汗が吹き出ていたが、もっともひどいのは
背骨が折れるのではないかという恐怖だった。彼は歯を食いしばり、鼻で荒い息をしながらできるだけ静かにしようと試みた。
(16)
「君は恐れている」オブライエンが言った。「今にどこかが折れてしまうことを。特にそれが背骨ではないかと恐れている。
脊椎が折れてバラバラになり、そこから髄液がこぼれ落ちる様子を鮮明に思い描いている。それが今、君が考えていることだろう? ウィンストン」
(17) ウィンストンは答えなかった。
オブライエンがダイヤルの目盛りを下げる。痛みの波はそれが来たときと同じくらいすばやく引いていった。
(18)
「今のが40だ」オブライエンが言った。「見ての通り
このダイヤルには数字が100まである。私たちの会話中、私はいつでも君に好きなだけの痛みを与えることができるということを憶えていたまえ。もし君が嘘をついたり、どうにかして誤魔化そうとしたり、普段と比べて物分かりが悪かったりすれば即座に君は痛みで悲鳴を上げることになる。
わかったかね?」
(19)
「はい」ウィンストンは言った。
(20)
オブライエンの態度がすこしだけ和らいだ。彼は眼鏡を思慮深げに直すと1、2歩動いた。次に彼が話しだした時、その声は穏やかで我慢強いものだった。漂わせる雰囲気はまるで医者か教師、あるいは牧師のようですらあり、罰を与えるというよりも説明し、説得しようとしているかのようだった。
(21)
「君には十分に時間をかけるつもりだよ。ウィンストン」彼は言った。「君にはそれだけの価値があるからだ。君は自分のどこが問題か完璧に理解している。何年もの間、君はそれを知っていた。それを押し殺してきたようだがね。
君の精神は狂っている。記憶障害に苦しんでいるんだ。現実の出来事を記憶できず、実際には起きていない出来事を記憶していると思い込んでいる。
幸運なことにこれは治療可能だ。自分だけで治すことは決してできない。君がそれを望んでいないからだ。君ができないでいる決断は実はそんなに大変なことではないんだよ。
君がその病気を美徳だと思い込んで、今でも固執していることはよくわかっている。ちょっと例をあげてみよう。今、オセアニアが戦争をしている国は?」
(22)
「私が逮捕されたときにはオセアニアはイースタシアと戦争をしていました」
(23) 「そう。イースタシアとだ。そして
オセアニアはずっとイースタシアと戦争してきたのだ。そうだね?」
(24) ウィンストンは息を吸った。彼はしゃべろうと口を開いたが何も言えない。ダイヤルから目を離すことができなかった。
(25) 「お願いだから真実を言ってくれ。ウィンストン。
君にとっての真実だ。君が憶えていると思っていることを話してくれ」
(26) 「私が憶えているのは、私が逮捕される一週間前まで私たちはイースタシアとは全く戦争状態になかったということです。私たちは彼らと同盟を結んでいた。
戦争の相手はユーラシアだった。それはもう4年も続いていた。その前は・・・」
(27)
オブライエンが手を上げて彼を止めた。
(28)
「別の例をあげよう」彼が言った。「数年前、君は非常に深刻な妄想を抱いたはずだ。
三人の男、ジョーンズ、アーロンソン、ラザフォードという名の三人のかつての党員・・・可能な限りの全てを自白した後に裏切りと破壊活動を理由に処刑された男たち・・・が
嫌疑をかけられた罪状について無罪だと信じ込んだ。彼らの自白が間違っていることを示す、疑いようのない証拠書類を見たと君は信じ込んだ。
そのことを示す写真が存在するという幻覚を見たのだ。君は実際にそれを手にしたと信じ込んだ。それはこんな写真だ」
(29) 長方形の新聞の切り抜きがオブライエンの指の先にあった。5秒ほどの間、それはウィンストンの視界にはいった。それは一枚の写真で、見間違うはずもなかった。
あの写真だ。それは11年前に彼が偶然手にし即座に破棄した、ニューヨークでの会合に出席しているジョーンズ、アーロンソン、そしてラザフォードの写真のコピーだった。つかの間、それは彼の目の前に置かれ、また視界から消えた。しかし確かに見た。間違いなく見たのだ!彼は上半身の自由を求めてを体をねじり、痛みを伴う虚しい努力をした。どの方向だろうと1センチも動かすことはできなかった。その時ばかりは彼はあのダイヤルのことさえ忘れた。彼の頭にあることはあの写真をまた手に取ること、それが叶わないならばもう一度目にすることだけだった。
(30)
「やっぱりあったんだ!」彼は叫んだ。
(31)
「いいや」オブライエンが言った。
(32) 彼は部屋の向こうに歩いていった。向こうの壁には
記憶の穴があった。オブライエンが蓋を開ける。誰の目にも映ること無く紙切れが暖かい空気にまかれ、炎の光の中に消えて入った。オブライエンが壁の方から戻ってきた。
(33)
「灰だ」彼は言った。「灰と見分けることすらできない。塵だな。
あれは存在しないし、今までも存在したことなどない」
(34) 「しかし確かにあった!
確かに存在するぞ!記憶の中に存在する。私が憶えている。あなたも憶えているはずだ」
(35)
「私は憶えていない」オブライエンが言った。
(36) ウィンストンの心は沈んだ。
二重思考だ。彼は致命的なまでの無力感を感じた。もしオブライエンが嘘をついていると確信できれば大した問題ではなかった。しかしオブライエンが本当に写真のことを忘れているということも十分にあり得るのだ。そしてもしそうならば、
彼は既に自分の記憶を否定したことも忘れているし、忘れたということも忘れているだろう。それがいかさまだと、どうやって確認すればいい?頭の中でそういった
常軌を逸した変調が本当に起こることだってあり得るだろう。その考えに彼は打ちひしがれた。
(37) オブライエンが考え込むようにしながら彼を見下ろしていた。
わがままだが将来有望な子供に罰を与える教師のような雰囲気を、前にも増して漂わせている。
(38)
「過去のコントロールについての党のスローガンがある」彼が言った。
「よければ暗唱してくれないか」
(39)
「過去を制する者が未来を制する。現在を制する者が過去を制する」ウィンストンは素直に暗唱した。
(40)
「現在を制する者が過去を制する」オブライエンが同意するようにゆっくりと頷きながら言った。
「過去は実在するというのが君の意見だな。ウィンストン?」
(41) 再び無力感がウィンストンを襲った。
彼の目がダイヤルの方をちらりと見た。肯定と否定どちらが彼を痛みから救う答えなのかわからなかった。
もう自分がどちらを真実だと信じているのかもわからなかった。
(42) オブライエンがかすかに微笑んだ。
「君は形而上学者じゃない。ウィンストン」彼は言った。「
存在ということが何を意味するのか考えなくてもいい。もっと正確に言おうか。過去というのは具体的に空間上に存在するか?
物質世界のどこかに、過去が今なお進行中である場所があるか?」
(43)
「無いです」
(44) 「それでは仮に存在するとして、
過去はどこに存在するのだ?」
(45)
「記録の中に。それは書き留められています」
(46) 「記録の中。それから・・・?」
(47)
「頭の中に。人間の記憶の中に」
(48)
「記憶の中。よろしい。私たち党は全ての記録をコントロールしているし、すべての記憶をコントロールしている。それでは私たちは過去をコントロールしているのではないかね?」
(49)
「しかし人々が物事を記憶することをどうやってやめさせるのです?」一瞬ダイヤルのことを忘れてウィンストンはまた叫んだ。「それは無意識におこなわれる。自らの手の及ばないことです。どうやって記憶をコントロールできるのです?
あなたは私の記憶さえコントロールできていない!」
(50) オブライエンの態度がまた厳しいものになった。彼の手はダイヤルの上に置かれていた。
(51)
「反対だ」彼が言った。「
コントロールできていないのは君の方だ。そのせいで君はここに連れて来られたんだ。
君がここにいるのは、君が謙虚さと自制心を失ったためなんだぞ。君は正気の代償である服従行為をおこなおうとしなかった。
錯乱し、少数派となることを選択した。鍛錬された精神だけが
現実を認識することができるのだ、ウィンストン。君は現実とは何か実体がある、外部的な、独自の真実性を持つ存在だと信じた。さらには
現実の本質は自明なものだと信じた。君が何かを見たと信じ込んだ時には、他の皆も君と同じ物を見ているはずだと考えている訳だ。しかし君に教えてやろう、ウィンストン。現実とは外部にあるものではないのだ。
現実とは人間の頭の中にだけ存在するものだ。それ以外のどこにも存在しない。個人の頭の中に、ということではないぞ。それでは思い違いが起きるし、どちらにしても死ねばすぐに消えてしまう。集合体であり、不滅である党の精神の中にだけ存在するのだ。
党が真実だと思うことは何であれ真実だ。党の目を通して見る以外には現実を見ることは不可能なのだ。これこそ君が学び直さなければならない事実だ、ウィンストン。そしてそれには
自己の滅却と努力が必要だ。正気になるためには自分に対して謙虚でなければならない」
(52) 自分の言っていることを
理解する時間を与えるかのように、彼はしばらく黙った。
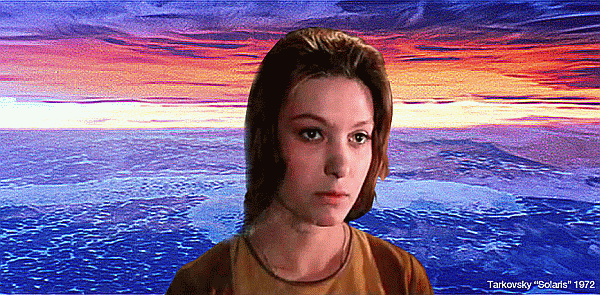
(53) 「君は自分の日記にこう書いたことを憶えているか?」彼は続けた。「
『自由とは2足す2が4だと言える自由だ』」
(54) 「ええ」ウィンストンは言った。
(55) オブライエンは手の甲を見せながら左手を上げた。親指を折り、4本の指は伸ばしている。
(56)
「私は何本の指を立てている、ウィンストン?」
(57)
「4本です」
(58)
「それではもし党が4本ではなく5本だと言ったら・・・その時は何本だ?」
(59) 「4本です」
(60)
痛みの声で言葉は途切れた。ダイヤルの針は
55まで上がっていた。ウィンストンの体中から汗が噴き出る。空気が彼の肺に襲いかかり、うめき声となって出て行く。歯を食いしばっているにも関わらず低いうめき声が漏れるのを止めることができなかった。
(61) オブライエンが4本の指を立てたまま彼を見つめていた。レバーが戻される。今度は痛みがわずかに和らいだだけだった。
(62) 「指は何本だ、ウィンストン?」
(63)
「4本です」
(64) 針が
60まで上がった。
(65) 「指は何本だ、ウィンストン?」
(66)
「4本!4本です!他にどう言えばいいんですか?4本だ!」
(67) 針がまた上がったことは間違いなかったが彼はもう見ていなかった。重苦しく厳めしい顔と4本の指が彼の視界を埋めていた。4本の指が彼の目の前に柱のように巨大にそびえ立っている。それはぼやけ、震えて見えたが明らかに4本だった。
(68) 「指は何本だ、ウィンストン?」
(69)
「4本だ!止めろ、止めてくれ!どうしたいっていうんだ?4本!4本だ!」
(70) 「指は何本だ、ウィンストン?」
(71)
「5本!5本!5本だ!」
(72) 「いいや、ウィンストン。そんなのは無駄だ。
君は嘘をついている。君はまだ4本だと考えている。指は何本だ、さあ?」
(73)
「4本!4本!4本!あなたの好きなだけだ。だから止めてくれ。痛みを止めろ!」
(74) 気がつくとオブライエンの腕で肩を支えられながら彼は座っていた。おそらくほんの数秒だが
意識を失っていたのだろう。彼の体をつなぎとめていた拘束具は緩められていた。ひどく寒く、体の震えが止まらずに歯がかちかちと鳴って、
頬を涙が伝っていった。しばらくの間、彼は赤ん坊のようにオブライエンにしがみついた。肩に回された大きな手が奇妙に安心感を与えた。
彼はオブライエンを自分の庇護者のように感じた。痛みはどこか外部の別の源から到来したもので彼をそれから救ってくれるのはオブライエンなのだ。
(75)
「君は物覚えが悪いな、ウィンストン」オブライエンが穏やかに言った。
(76) 「どうすればいいって言うんだ?」彼は泣きじゃくった。
「目の前にある物をどうやって見ればいいって言うんだ?2足す2は4だ」
(77) 「時には、ウィンストン。
時には5にもなるんだよ。時には3にもなる。時には同時にそれら全てにもなるんだ。君は頑張らなくちゃならない。
正気になるのは簡単じゃない」
(78)
彼はウィンストンをベッドに寝かせた。手足の拘束がまたきつくなったが痛みは引き、震えが止まり、不快な気分と悪寒だけが残った。
今までずっと動かずに立っていた白い上着の男にオブライエンが頭で合図した。白い上着の男はかがみこんでウィンストンの目を覗き込み、脈をとったり、胸に耳をつけたり、そこかしこを触って調べたりした後、
オブライエンに頷いてみせた。
(79)
「もう一度だ」オブライエンが言った。
(80)
痛みがウィンストンの体に流れ込んだ。針が
70から
75あたりを指していることは間違いない。
今度は彼は目を閉じた。指がまだそこにあること、そしてまだ4本であることが彼にはわかっていた。
もっとも重要なことは、この痙攣が終わるまでどうやって生き延びるかだった。自分が叫び声を上げているのかどうかもわからなかった。また痛みが引いてゆく。彼は目を開けた。オブライエンがレバーを下げていた。
(81)
「指は何本だ、ウィンストン?」
(82) 「4本です。4本あるように思います。
5本に見えればいいのに。5本に見えるように頑張っているのですが」
(83) 「君はどうしたい。5本見えていると私を説得したいか?それとも
本当にそう見たいと思っているのか?」
(84)
「本当にそう見たいと思っています」
(85)
「もう一度だ」オブライエンが言った。
(86) おそらく針は
80・・・いや
90を指していた。ウィンストンの記憶は断続的に途切れ、なぜ痛みが起きているのかわからなくなった。
彼の痙攣するまぶたの裏では林立する指が舞い踊り、揺らめいては他の指の後ろに消えたり現れたりしていた。彼は訳もわからずそれを数えようとしていた。それを数え上げることができないことはよくわかっていたが、どうした訳か不思議と4か5のどちらかであることはわかっていた。痛みがまた過ぎ去った。彼は目を開けたが、見えているものは同じだった。動きまわる木々のような無数の指が重なり合いながらそれぞれの方向に流れ去っていった。彼はまた目を閉じた。
(87)
「私は指を何本立てている、ウィンストン?」
(88) 「わかりません。私にはわかりません。
もう一度やられたら私は死んでしまいます。4本なのか、5本なのか、6本なのか・・・本当に私にはわからないのです」
(89)
「よろしい」オブライエンが言った。
(90)
注射針がウィンストンの腕に滑り込んだ。直後に充足した癒されるような暖かさが彼の体中に広がった。痛みは既に半分忘れ去られていた。彼は目を開くと感謝するようにオブライエンを見上げた。重厚ではっきりした顔立ちはとても醜悪でありながら同時に非常に知性的に見え、彼の心はひっくり返ったようになった。もし身動き出来れば手を伸ばしてオブライエンの腕に置いただろう。
今ほど彼に敬愛を感じたことはなかったし、それはただたんに彼が痛みを止めてくれたからではなかった。オブライエンが友人なのか敵なのかは心底どうでもいいという、以前と同じ感情が戻ってきた。
オブライエンは会話するに値する人物なのだ。おそらく人間は愛される以上に理解されることを望むのだろう。
オブライエンは彼を拷問によって狂気の縁に追い詰めた。そして近いうちに間違いなく彼を死に追いやるだろう。しかしそれも問題ではなかった。
ある意味ではそれは友情よりも深いもので、二人は親友だったのだ。実際には言葉を交わしたことなど無いのにも関わらず、どこかで二人は会って話したことがあるのだ。
同じことを考えていると表情で示すようにしながら、オブライエンは彼を見下ろしていた。彼がしゃべり始めたとき、それは気安い会話のような口調だった。
(91) 「自分がどこにいるかわかるか、ウィンストン?」彼が言った。
(92) 「わかりません。推測はできます。愛情省の中です」
(93) 「どれくらいの間、ここにいるかわかるかね?」
(94) 「わかりません。数日か、数週間か、数ヶ月か・・・数ヶ月だと思います」
(95)
「それではなぜ我々は人々をこの場所に連れてくると思うかね?」
(96) 「自白させるためです」
(97) 「いいや。そんな理由ではないね。もう一度、考えて」
(98) 「罰を与えるためです」
(99)
「違う!」オブライエンが声を荒らげた。彼の声が大きく変わり、その顔が突然、厳しく感情的なもに変わった。「違うんだ!
たんに自白を引き出したり、罰を与えるためではない。なぜ君をここに連れてきたのか、教えてあげようか?
君を治療するためだ!君を正気に戻すためだ!わかるかね、ウィンストン?我々がここに連れてきた者で、
治療が終わらないうちに我々の手を離れた者は未だかつて一人もいないのだよ。我々は君が犯した馬鹿げた犯罪などに興味はない。党は目に見える活動には興味がないんだ。我々が関心があるのはその思想だけだ。
我々はたんに敵を滅ぼすのではなく、変化させるのだ。私の言っていることがわかるかね?」

(100)
彼はウィンストンの上に屈み込むようにした。近づいた顔は巨大に見え、下から見ているせいでぞっとするほど醜かった。さらに言えばそこには精神的な高揚感、
狂人のような激しさが満ち溢れていた。ウィンストンの心臓は再び縮こまった。もしそれができれば彼はベッドの奥深くに縮こまったことだろう。オブライエンはほんの気まぐれであのダイヤルをひねるだろうと彼は感じた。しかしオブライエンはきびすを返した。彼はその場で2、3歩行ったり来たりしてから少し落ち着いたようになって続けた。
(101) 「君がまず理解しなければならないことは、
ここでは殉教は存在しないということだ。君は過去の宗教迫害について読んだことがあるだろう。中世には異端審問があった。これは失敗だった。異端を根絶するために始まったにもかかわらず長続きさせる結果に終わった。
異端者を火あぶりにする度に1000もの他の者を立ち上がらせたのだ。なぜだと思う。異端審問では公開で処刑がおこなわれたからだ。そして異端者が改悛する前にそれがおこなわれたからだ。改悛しないからという理由で処刑をおこなったのだ。
人々はその真の信念を放棄しないがために死んでいった。当たり前のごとく全ての栄光は犠牲者に帰され、全ての恥辱は彼らを燃やした異端審問官に帰された。後世、20世紀には全体主義者と呼ばれる者たちが台頭した。ドイツのナチスやロシアのコミュニストだ。
ロシア人たちは異端審問がそうしたのよりもなお一層冷酷に異端者を迫害した。彼らは自分たちは過去の過ちに学んだと考えていた。
ともかく相手を殉教者にしてはいけないということは理解していたのだ。犠牲者を公開裁判に引き出す前に彼らは時間をかけて相手の尊厳を打ち壊した。彼らが卑しく卑屈で恥知らずになり、言われたことは何でも自白し、自分のことを卑下し、他の者を非難して言い逃れし、泣いて慈悲を請うまで拷問と孤独によって疲弊させたのだ。
しかしほんの数年でまた同じことが起きた。死んだ者は殉教者に祭り上げられその恥辱は忘れられた。
さあ、なぜだと思う?まずあげられるのは彼らの自白が明らかに強要されたものであり、虚偽であったということだ。
我々は同じ過ちは犯さない。ここで述べられた全ての自白は真実だ。我々がそれを真実にする。そしてもっとも重要なことは、
我々は死者が我々の敵対者として祭りあげられることを許さないということだ。後世の人間が君の正当性を証明してくれるとは考えないことだ、ウィンストン。後世の人間が君のことを耳にすることはない。
君はきれいに歴史の中から消し去られるだろう。我々は君を気体に変え、大気に送り出すだろう。君に関することは何も残されない。記録の上の名前も、生きている人間の頭の中の記憶もだ。君は過去からも未来からも消し去られる。
存在しなかったことになるのだ」
(102)
それではなぜ自分を拷問するのだろうか?ウィンストンは少し皮肉に思いながら考えた。まるでウィンストンが考えていることを声に出して喋ったかのようにオブライエンは歩みを止めた。彼の目を少し細めた大きな醜い顔が近づいてくる。
(103)
「君はこう考えている」彼が言った。「我々が君を完全に打ち殺してしまおうとしているなら、君が何を言おうが行おうが大した違いは無いじゃないか・・・
それならばなぜわざわざ君を取り調べるような面倒をおこなっているのか?君はそう考えているのではないかね?」
(104)
「ええ」ウィンストンは言った。
(105) オブライエンが薄く笑った。「
君は欠陥品だ。ウィンストン。ぬぐい去られなければならない汚点だ。我々は過去の迫害者とは違うとついさっき言わなかったか?我々は後ろ向きな服従にも、もっとも惨めな降伏にも満足しないのだよ。
君が最終的に我々に降伏するときには、それは君の自由意志によるものでなければならない。我々は異端者を打ち殺しはしない。相手は我々に抵抗しているのだ。抵抗を続ける限り、我々が相手を打ち殺すことは決してない。
我々は相手を転向させる。内面を捕縛する。矯正する。全ての悪徳と幻想を相手から焼き捨てる。
相手を我々の側に連れてくるのだ。ただの見せかけではなく誠心誠意、全身全霊でそう思うようにさせるのだ。
殺す前に、我々は相手を我々の一員にするのだ。世界のどこであれ誤った思想が存在することに我々は耐えられない。たとえそれが秘密にされていようと、無力であろうとだ。死の瞬間であろうとどんな逸脱も許さない。古い時代には異端者は異端者のまま火刑へと歩み、そのさなかに歓喜と共に自らの異端を宣言した。あのロシアの粛清の犠牲者でさえ、その頭蓋骨の中に閉じ込めた反乱を手にしたまま銃殺へと続く廊下を歩んでいくことができた。しかし我々は、
吹き飛ばす前にその脳をまっとうなものにしてやるのだ。過去の
専制君主の命じるところは
「汝、かくあるべからず」だった。
全体主義者の命じるところは
「汝、かくあるべし」だった。
我々の命じるところは
「汝、かくなり」だ。我々がここに連れてきた人間で最後まで反抗を貫いた者は一人もいない。全員きれいに洗浄された。君がかつて無実を信じたあの哀れな三人の裏切り者・・・
ジョーンズ、アーロンソン、ラザフォード・・・さえも我々は最後には屈服させた。彼らの取り調べには私も参加したのだよ。彼らが次第に疲れ果て、泣き言を言い、へつらい、すすり泣くのを私は見た・・・最後にはそれは苦痛のためでも恐怖のためでもなく、ただ後悔のためだった。
我々の取り調べが終わったときには、彼らは完全な抜け殻だったよ。残されたものは自らの行為に対する後悔と、ビッグ・ブラザーに対する敬愛だけだった。その敬愛の深さを見ると感動するほどだったよ。
彼らは自分の精神が清らかなうちに死ねるよう早く撃ち殺してくれと懇願したんだ」
(106) 彼の声はまるで夢見るような調子になっていった。
狂人の熱狂を思わせる高揚感が彼の顔には浮かんでいた。演技ではない、彼は役者ではないのだ、自分の言ったことを全て信じている、そうウィンストンは思った。彼を何よりも憂鬱にさせるのは自らに対する知性的な劣等感だった。彼は重厚で優雅な姿が視界を出入りしつつ歩きまわるのを見守った。
オブライエンはすべての面で彼よりも大きな存在だった。彼が今まで考えてきたり、考えつく可能性のあったアイデアは全てとっくの昔にオブライエンが思いつき、調べ、却下しているのだ。
彼の頭脳はウィンストンの頭脳を内包しているのだ。しかしそうであるならば、
オブライエンは狂っているとは言えないのではないか?狂っているのは彼、ウィンストンの方だ。オブライエンが立ち止まり彼を見下ろした。その声はまた厳格なものになっていた。
(107) 「我々に全面降伏したからといって、
自分が助かるなどとは考えないことだ、ウィンストン。一度道を外れた者が見逃されたことなどいままで一度も無いのだ。それにたとえもし君が元の生活に戻ることを我々が選んだとしても、我々から逃げ出すことなど決してできはしないのだ。
ここで君に起きたことは永遠に続く。あらかじめ理解しておくことだな。
我々は君を取り返しの付かない状態にまで破壊する。君がこの先、千年生きるとしてもこれから君に起きることを元通りにすることはできない。
君が普通の人間と同じ感情を持つことは、もう二度と無い。君の内面にある物、全てが死ぬのだ。愛情も、友情も、生きる歓びも、笑いも、好奇心も、勇気も、高潔さも君が感じることは二度と無い。
君は空っぽになるのだ。君が空になるまで絞り上げ、
それから我々自身で君を満たしてあげよう」
(108) 彼は口を閉じると白い上着の男に合図した。ウィンストンは自分の頭の後ろに
なにか重そうな装置が設置されたことに気づいた。オブライエンがベッドの脇に腰掛けたので彼の顔の高さはウィンストンの顔とほとんど同じ高さになっていた。
(109)
「3000だ」彼がウィンストンの頭越しに白い上着の男に言った。
(110)
少し湿った感じがする二つの白いパッドが、ウィンストンのこめかみに貼りつけられる。彼は怯えた。痛みが、新しい種類の痛みが来るのだ。オブライエンはまるでいたわり、勇気づけるように手を彼の上に置いた。
(111)
「今度は痛みはない」彼が言った。
「しっかりと私を見ていたまえ」
(112)
その瞬間、とてつもない爆発が起きた。いや爆発のように思えただけかもしれない。何か大きな音がしたかどうかは定かではなかった。目も眩むような閃光が走ったことは確かだった。なぎ倒された感覚があるだけで痛みは感じなかった。それが起きた時、彼は既に横たわっていたというのに、奇妙なことに倒れこんだような感覚に襲われたのだ。
痛みを伴わないとてつもない爆風が彼を吹き飛ばしたのだ。視界の焦点が元に戻っていくに従って彼は自分が誰で、今どこにいるのかを思い出していき、自分を見つめる顔が誰なのかも思い出した。しかし、どこかに
大きな空白の領域があった。
まるで脳の一部が抜け落ちてしまったようだった。
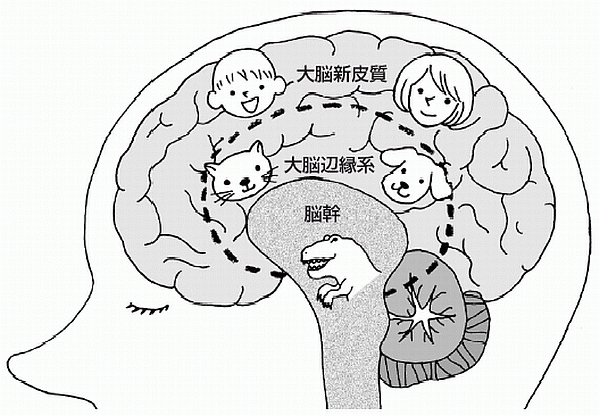
(113)
「時間はかからない」オブライエンが言った。
「私を見るんだ。オセアニアはどの国と戦争している?」
(114) ウィンストンは考えた。オセアニアという言葉が意味することや、自分がオセアニアの市民であることはわかった。同じようにユーラシアとイースタシアについても憶えている。しかし
誰が誰と戦争しているのか彼にはわからなかった。実際のところ、彼は戦争が起きているということさえ知らなかったのだ。
(115)
「思い出せません」
(116)
「オセアニアはイースタシアと戦争している。思い出したかね?」
(117)
「はい」
(118) 「オセアニアはずっとイースタシアと戦争を続けてきたのだ。君が生まれてからこれまで、党が誕生してからこれまで、有史以来、
この戦争は止むこと無く続いてきた。ずっと同じ戦争がだ。思い出したかね?」
(119)
「はい」
(120) 「11年前、君は裏切りを理由に死刑判決を受けた三人の男についての架空の話を作り出した。
君は彼らの無実を証明する紙切れを自分が見たように装った。そんな紙切れは存在しないのだ。
君がそれをでっち上げ、次第に自分でも信じるようになったのだ。今はもう初めてそれをでっち上げたその瞬間のことを君は思い出しているはずだ。
思い出したかね?」
(121)
「はい」
(122) 「ついさっき、私は君に指を立てて見せた。5本の指が見えていたはずだ。
思い出したかね?」
(123)
「はい」
(124) オブライエンは左手の指を立てた。親指は隠されている。
(125) 「
ほら、5本の指だ。5本の指が見えるかね?」
(126)
「はい」
(127) 彼の頭に浮かんだ風景が変わる前のつかのまの一瞬、彼には確かにそれが見えた。
少しも欠けたところ無く、5本の指が見えたのだ。それから全てが普通の状態に戻り、以前感じた恐怖や憎悪や困惑が一斉に舞い戻ってきた。しかしほんの一瞬だったが・・・どれくらいか定かではなかったが30秒くらいだろう・・・疑いのない確実な瞬間があった。そして一瞬とはいえ
オブライエンの新しい教えのそれぞれが空白の空間を満たし、絶対的な真実に変わり、必要とあらば2足す2は簡単に3にも5にもなったのだ。オブライエンが手を下ろす前にその瞬間は消えてしまい、再び経験することはできなかったが
記憶にとどめることはできた。まるでちょうど別の人間であった時の人生を鮮明に憶えているようだった。
(128)
「君にもわかっただろう」オブライエンが言った。
「どんなことでも可能なのだよ」
(129)
「はい」ウィンストンは答えた。
(130) オブライエンは満足気に立ち上がった。彼の左にいる白い上着の男がアンプルを割って注射器に吸い上げるのがウィンストンに見えた。オブライエンは微笑みながらウィンストンの方に顔を向けると、以前のあのやり方で鼻の上の眼鏡を直した。
(131) 「君は自分の日記にこう書いたことを憶えているかね?」彼は言った。「私が味方だろうが敵だろうが構わない。少
なくとも君を理解し会話を交わすことのできる人物だ、と。君は正しい。君との会話は楽しかったよ。君の考えは実に面白い。
私の考えとも似ている。君が正気でないということを除けばだがね。さて話し合いを終える前になにか質問があれば答えよう」
(132)
「どんな質問でも?」
(133)
「なんでも」彼はウィンストンの目があのダイヤルに向けられていることに気づいた。「スイッチは切られているよ。
最初の質問は何かね?」
(134)
「ジュリアに何をしたんですか?」ウィンストンは言った。
(135) オブライエンが再び微笑んだ。「
彼女は君を裏切ったぞ、ウィンストン。
すぐさま・・・何の躊躇もなくな。あんなに早く寝返る者はあまり見たことがない。君が彼女を見たとしても、そう見分けるのは難しいだろう。彼女の反抗心や欺瞞、愚かさや汚れた心の全て・・・全てが彼女から焼き払われたのだ。
教科書通りの完璧な転向だよ」
(136)
「あなたが拷問したのですか?」
(137) オブライエンは答えなかった。
「次の質問は」彼は言った。
(138) 「ビッグ・ブラザーは実在するのですか?」
(139) 「もちろん彼は実在する。党が実在するようにだ。
ビッグ・ブラザーは党を体現するものなのだ」
(140) 「彼は私が実在するのと同じように実在するのですか?」
(141)
「君は実在していない」オブライエンは言った。
(142) 再び無力感が彼を襲った。彼には自らの非実在性を証明する論理が存在するということがわかったし、それがどのようなものか想像もできた。しかしそんなことは無意味だ。
それはたんなる言葉遊びにしか過ぎない。「君は実在していない」という命題には論理的な矛盾があるのではないだろうか?しかしそんなことを言ったところで何になるだろうか?オブライエンが彼を論破するために繰り広げるであろう
答えのでない狂った議論について考えると、彼の頭脳は次第にしなびてゆくようだった。
(143)
「私は私が実在すると思っています」彼は弱々しく言った。「私は自分のアイデンティティーを意識できます。私は生まれ、そして死ぬでしょう。私には腕も足もあります。
私は空間上で特定の位置を占めています。他の物体が同時に同じ位置を占めることはできません。そういった意味でビッグ・ブラザーは実在しているのですか?」
(144) 「それは重要なことではない。彼は実在する」
(145)
「それではビッグ・ブラザーは死ぬことがあるのですか?」
(146)
「もちろん死なない。どうやって死ぬというのだ?次の質問だ」
(147) 「ブラザーフッドは実在するのですか?」
(148) 「ウィンストン、
君がそれを知ることは永遠にない。たとえ君の処分が終わった時に我々が君を自由の身にすることを選び、君が90歳まで生きたとしてもその質問の答えがイエスなのかノーなのかを君が知ることはない。
君が生きている間、それは解けない難問として君の頭の中に残り続けるだろうな」
(149) ウィンストンは黙ったまま横たわっていた。胸の上下動が少し速くなる。彼はまだ
一番最初に頭に浮かんだ質問をしていなかった。尋ねようとしたがまるで舌がそれを拒否しているようだった。オブライエンの顔には楽しんでいるかのような表情が浮かんでいた。その眼鏡まで皮肉を湛えた輝きをまとっているようだ。彼は知っている。ウィンストンは唐突に思った。彼は自分が何を尋ねようとしているのか知っているのだ!そう思った瞬間、言葉が彼から飛び出した。
(150)
「101号室には何があるのですか?」
(151) オブライエンの顔に浮かんだ表情は変わらなかった。彼はそっけなく答えた。
(152)
「ウィンストン、君は101号室に何があるのか知っている。誰だって101号室に何があるのか知っている」
(153) 彼は白い上着の男に向かって指を上げてみせた。
会話は終わったのだ。注射針がウィンストンの腕に突き刺さった。直後に
彼は深い眠りに落ちていった。